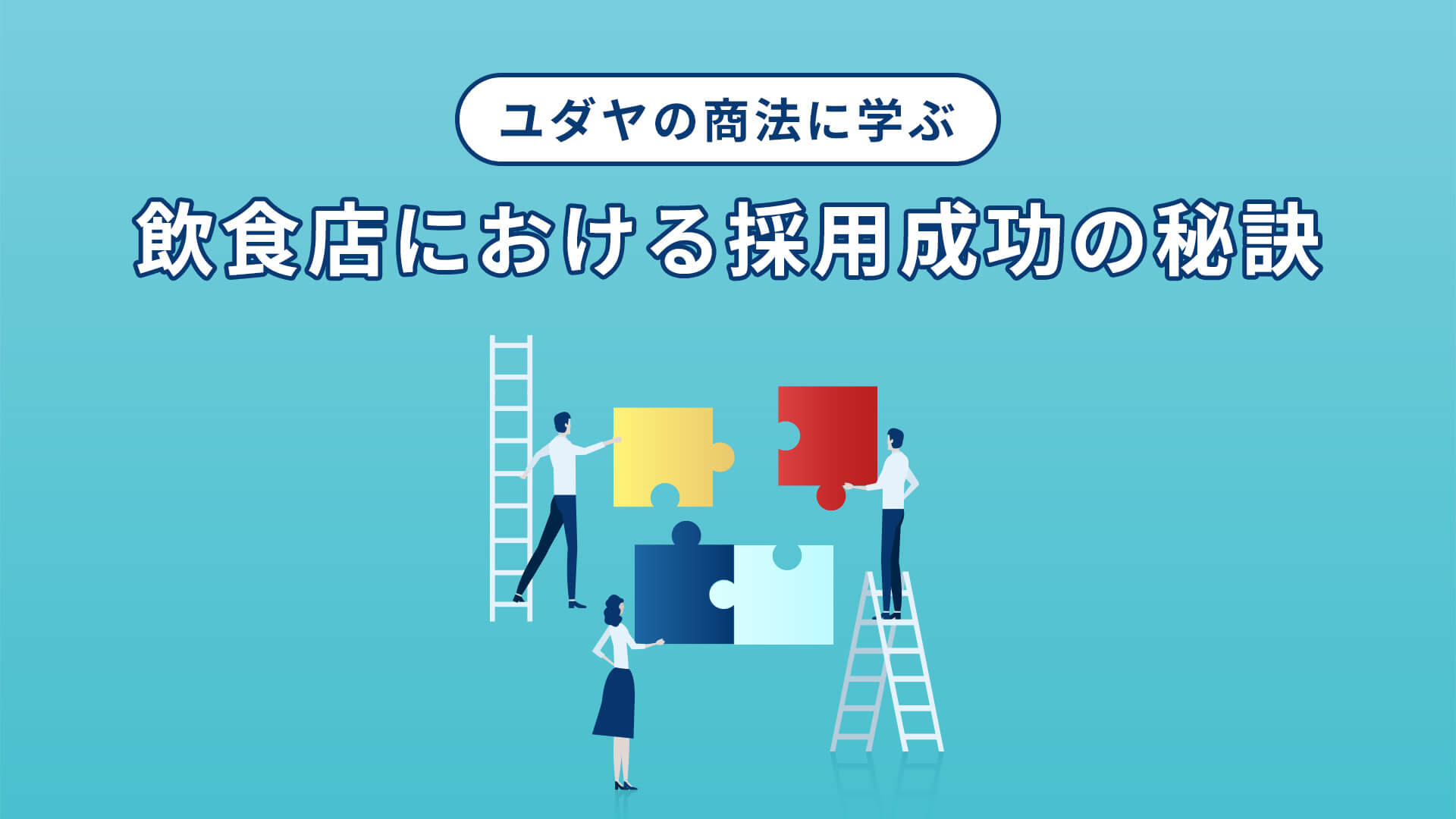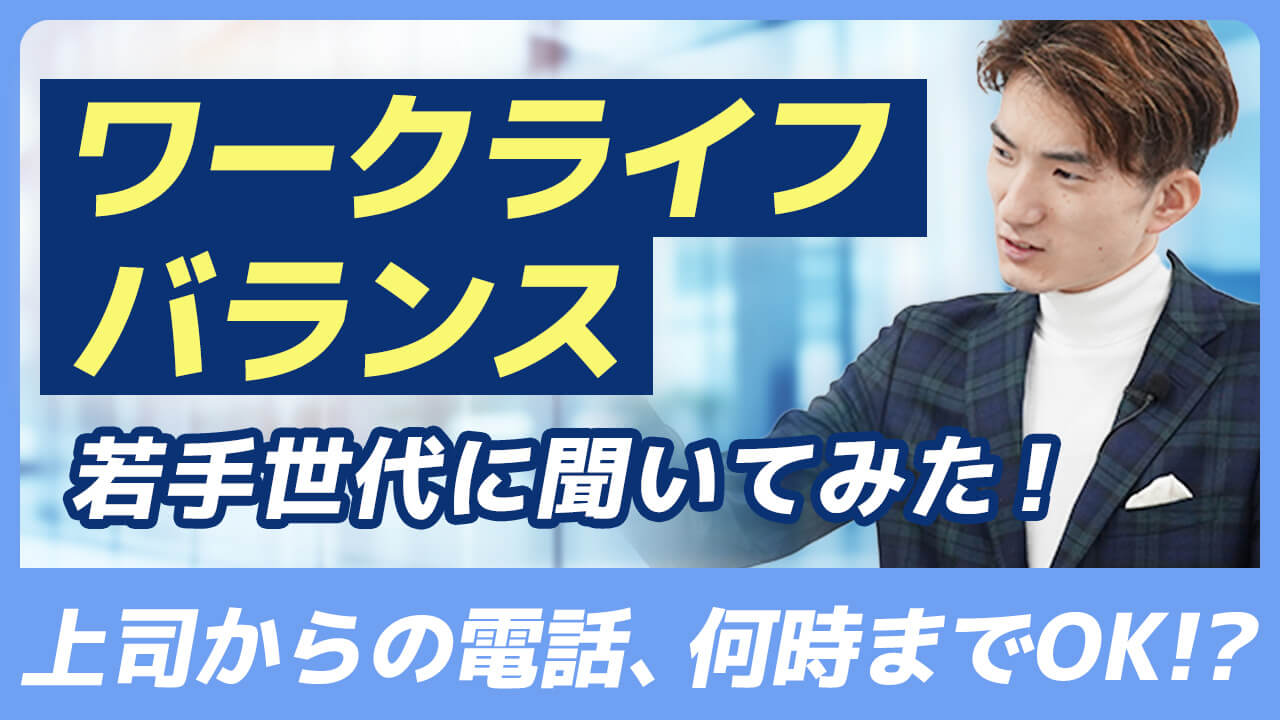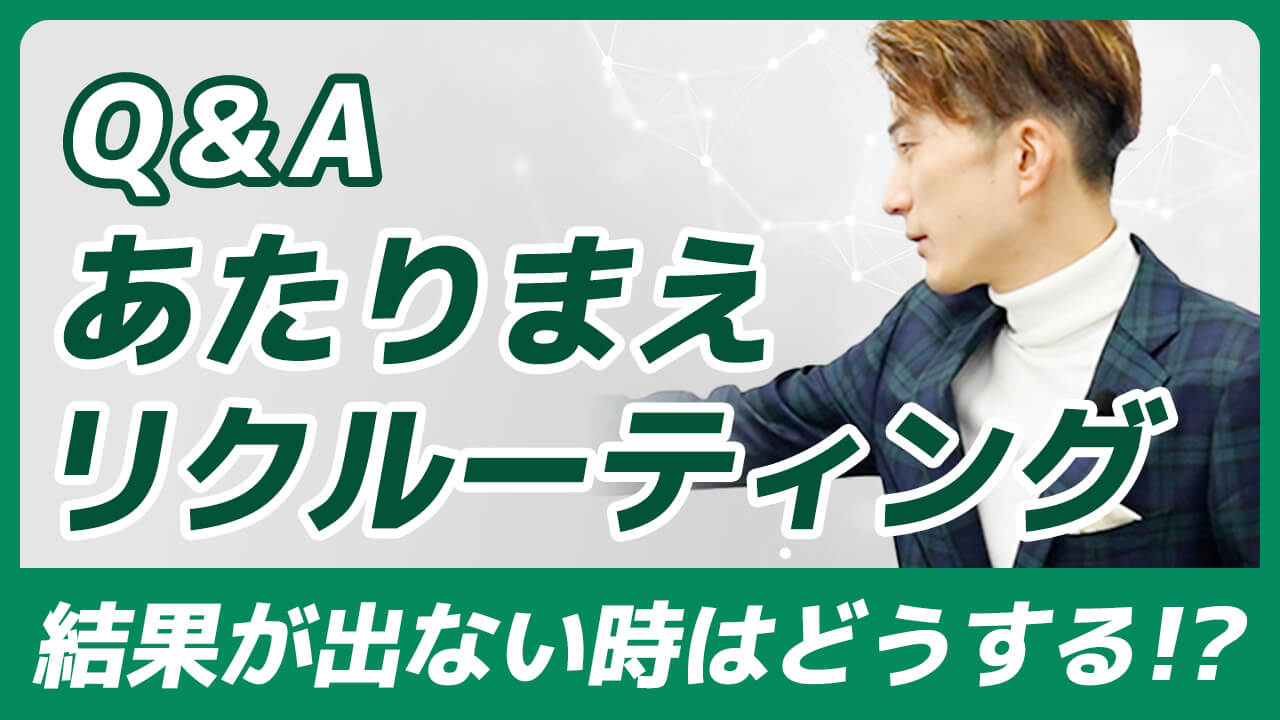「採用代行を導入したいけど、費用が気になる…」
「面接代行の料金って、本当に投資する価値があるの?」
人材不足が深刻化し、採用競争が激化する中、多くの企業が採用業務の効率化を模索しています。特に、専任の採用担当者がいない中小企業や、大量採用に迫られる成長企業では、採用代行(RPO)の導入を検討する声が増えています。
しかし、RPO費用や面接代行料金は決して安くありません。本記事では、採用代行の基礎知識から料金体系、導入のメリット・デメリットまで詳しく解説します。
自社に最適な採用代行サービスを選ぶ際の判断材料としてご活用ください!
監修者

あたりまえリクルーティング
HR研究室 広報
相沢みか
あらゆる手段を使って採用を成功に導くために!
あたりまえリクルーティングのHR研究室にて広報を務めております。ひとり広報さんの、「困った」「分からない」を一緒に解決するお手伝いをしておりますのでよろしくお願いいたします。

あたりまえリクルーティング
HR研究室 広報
相沢みか
あらゆる手段を使って採用を成功に導くために!
あたりまえリクルーティングのHR研究室にて広報を務めております。ひとり広報さんの、「困った」「分からない」を一緒に解決するお手伝いをしておりますのでよろしくお願いいたします。
目次
なぜ採用できない?根本的な原因と対策を徹底解説
昨今の採用市場では、多くの企業が「採用できない」という課題に直面しています。特に中小企業では人材確保に苦戦するケースが増えているのが現状です。
採用がうまくいかない背景には、企業側の体制や取り組み方に課題があることも少なくありません。
ここでは、採用できない原因を深掘りしながら、具体的な対策までわかりやすく解説していきます。まずは、よくある4つの課題から見ていきましょう。
採用の目的や評価基準が定まっていない
多くの企業で「とにかく人手が足りない」という理由だけで採用を始めてしまいがち。でも、それは大きな落とし穴です。採用の目的があいまいだと、どんな人材が必要なのかも不明確になってしまいます。
特に気をつけたいのが、面接官による評価のバラつきです。採用基準が明確でないと、人によって合否の判断が大きく変わってしまいます。また、必要なスキルや経験を具体的に定義していないケースも目立ちます。
採用成功の第一歩は、なぜ採用が必要なのか、どんな人材を求めているのか、を組織全体で共有することから始まります。具体的な基準を設けることで、より効率的な採用活動が可能になりますよ。
市場の変化に対応できていない
採用市場は日々変化しています。昔ながらの採用方法にこだわっていると、優秀な人材の確保は難しくなるばかり。特に給与水準は要注意です。世間相場を把握していないと、応募者が集まらないのも当然といえます。
最近では、働き方の柔軟性も重要なポイント。在宅勤務やフレックスタイム制など、多様な働き方に対応できない企業は、若手人材からの支持を得られにくいのが現状です。
また、業界のトレンドや競合他社の動向把握も欠かせません。採用市場で勝ち抜くためには、常にアンテナを張り、変化に柔軟に対応することが求められています。情報収集を怠らず、適切な対策を打っていきましょう。
選考の仕組みが時代遅れになっている
応募者とのやり取りがメールだけ、面接日程調整に時間がかかる、選考結果の連絡が遅い…。こうした時代遅れの選考プロセスが、せっかくの応募者を逃す原因になっています。
特に最近の若手求職者は、スピーディーな選考を好む傾向が強いもの。選考期間が長引くと、その間に他社の内定を得てしまうことも。オンライン面接の導入など、デジタル化への対応も必須です。
選考の仕組みを見直すポイントは主に3つです。
- 応募者とのコミュニケーション方法の改善
- 選考プロセスの簡略化
- 合否連絡の迅速化
これらを整備することで、応募者の離脱を防ぎ、採用成功率を高めることができます。
受入体制が整っていない
せっかく採用できても、その後のフォローが不十分では早期退職のリスクが高まります。特に研修プログラムの充実度は、新入社員の定着率に大きく影響するポイント。
受入体制の不備でよく見られる問題は以下のとおりです。
- 体系的な研修の欠如
- メンターの不在
- 配属部署との連携不足
- 将来のキャリアパスが不明確
採用活動と同じくらい重要なのが、入社後のサポート体制。新しい環境での不安を和らげ、スムーズな職場適応を支援する仕組みづくりが欠かせません。特に入社後3ヶ月は手厚いフォローを心がけましょう。
【要注意】採用で陥りやすい4つの失敗パターン
採用活動でつまずく企業の多くは、似たような失敗パターンに陥っています。応募者が集まらない、面接辞退が多い、内定辞退が続く、早期退職が増える…。こうした問題は、適切な対策を講じることで防ぐことができます。
ここからは、採用でよくある失敗パターンとその解決策について詳しく見ていきましょう。自社の状況と照らし合わせながら、改善のヒントを見つけてください。
応募者が全く集まらない
求人を出しても応募が来ない…。これは多くの企業が直面する悩みの種です。主な原因として、求人媒体の選び方を間違えているケースが目立ちます。ターゲットとする人材がよく利用する媒体を選ぶことが重要です。
また、求人原稿の内容も要注意。「仕事内容」「求める人材像」「給与」など、具体的な情報が不足していると応募につながりません。特に以下の点に注意が必要です。
- 魅力的な仕事内容の具体的な説明
- 実現可能な募集条件の設定
- 会社の特徴や強みのアピール
採用時期も大切なポイント。業界の繁忙期を避けたり、転職シーズンを狙ったりと、戦略的な募集タイミングの設定が求められます。
面接辞退が続出する
面接の日程調整が済んでも、直前のキャンセルや無断欠席が相次ぐ…。この状況には、選考プロセスの問題が隠れています。特に選考の遅さは致命的。今の求職者は複数社を並行して受けているため、対応の遅い企業からは自然と離れていきます。
改善のポイントは以下の3つ。
- 面接日程の柔軟な設定
- こまめな状況確認と情報提供
- オンライン面接の活用
また、面接官の態度や対応も重要です。応募者に企業の魅力が十分に伝わっていないと、次の選考に進むモチベーションが下がってしまいます。
内定辞退が後を絶たない
内定は出したものの、辞退されてしまうケース。これには主に、以下のような理由が考えられます。
- 他社との条件面での見劣り
- 入社後のキャリアパスが不明確
- 内定者フォローの不足
- 競合他社からの内定獲得
特に重要なのが「内定者フォロー」です。内定から入社までの期間、放置されていると不安が募るもの。定期的な連絡や、先輩社員との交流機会の提供など、きめ細かなフォローが効果的です。
入社後すぐに退職してしまう
せっかく採用できても、入社後すぐに退職されては元も子もありません。早期退職の主な原因は、求人票や面接時の説明と実態とのギャップです。
よくあるミスマッチの例:
- 残業時間の実態が説明と異なる
- 仕事内容が想像していたものと違う
- 職場の雰囲気が合わない
- 教育体制が不十分
これらを防ぐには、採用段階での「正直な情報開示」が重要です。確かに、良い面だけを伝えたくなる気持ちはわかります。しかし、入社後のギャップによる退職のほうが、企業にとってはより大きなダメージとなるのです。
採用できないとどうなる?企業が直面する4つのリスク
「採用できない」状態を放置すると、企業にとって深刻な問題に発展する可能性があります。人材不足は、単に「人手が足りない」だけでなく、企業の成長や従業員の健康、職場環境など、さまざまな面に影響を及ぼします。
ここでは、採用難が企業にもたらす4つの重大なリスクについて解説します。これらの問題が起きる前に、適切な対策を講じることが重要です。
事業の成長が止まる
人材不足は、企業の成長に直接的なブレーキをかけます。新規プロジェクトの立ち上げを延期せざるを得なかったり、せっかくの事業拡大のチャンスを逃したり…。
人手不足による具体的な影響は以下のとおり。
- 商品開発の遅れ
- 新規顧客への対応力低下
- 既存事業の縮小
- 競合他社への遅れ
特に深刻なのが、イノベーションの機会損失です。人材不足で目の前の業務に追われ、新しいことにチャレンジする余裕がなくなってしまいます。
現場の社員が疲弊する
人手が不足すると、既存の社員への負担が必然的に増加します。その結果、以下のような問題が発生しがちです。
- 慢性的な残業
- 休暇が取れない
- メンタルヘルスの悪化
- ミスの増加
特に注意が必要なのが、「負担増→体調不良→休職→さらなる人手不足」という悪循環です。一人の離職が他のメンバーの負担を増やし、連鎖的な退職を引き起こす可能性もあります。
職場の雰囲気が悪くなる
人手不足は、職場の雰囲気にも大きな影響を与えます。「人が足りない」というストレスから、些細なことでイライラが募り、職場の人間関係が悪化していきます。
現場でよく見られる変化:
- 部署間の対立増加
- コミュニケーション不足
- 愚痴や不満の増加
- モチベーション低下
特に危険なのが、余裕のなさからハラスメントが発生するケースです。「早く仕事を覚えろ」という焦りが、新入社員への過度な叱責につながることも。こうした状況を放置すると、さらなる退職者を生む原因となってしまいます。
競合他社に後れを取る
採用難が続くと、市場での競争力が徐々に低下していきます。特に同業他社と比べて人材確保が遅れると、その差は年々広がっていく傾向にあります。
競争力低下の具体例:
- 新技術への対応の遅れ
- サービス品質の低下
- 業界内での評判悪化
- 優秀な人材の流出
一度競争力が低下すると、その回復には多大な時間と労力が必要です。採用の問題は、企業の将来を左右する重要な経営課題として捉える必要があるのです。
採用成功へ導く!実践的な改善ステップ5選
ここまで採用の課題やリスクについて見てきましたが、では具体的にどう改善すればよいのでしょうか。ここからは、採用成功に向けた具体的な施策をご紹介します。
すべてを一度に実施するのは難しいかもしれません。自社の状況に合わせて、優先順位をつけながら段階的に取り組んでいくことをおすすめします。
求める人物像を明確にする
「いい人材」という漠然とした基準では、良い採用はできません。採用成功の第一歩は、具体的な人物像を定めることから始まります。
明確にすべきポイント:
- 必要なスキルや資格
- 求める経験年数
- 重視する人物特性
- 配属先での役割
ただし、あまりに理想が高すぎる人物像を描くのは禁物です。市場の実態を踏まえた現実的な要件設定が重要です。また、部署ごとに求める人物像が異なる場合は、それぞれに応じた基準を設けましょう。
選考のスピードを上げる
今の採用市場で最も重要なのが、選考のスピードアップです。優秀な人材ほど、複数の企業を同時に受けているもの。対応が遅いと、他社に先を越されてしまいます。
スピードアップのコツ:
- 選考ステップの簡略化
- 面接日程の柔軟な調整
- オンライン面接の活用
- 意思決定プロセスの短縮
ただし、スピード重視で選考の質を落としては本末転倒です。適切な見極めができる範囲で、最短の選考プロセスを設計することが大切です。
企業の魅力を効果的に発信する
採用市場では、企業の知名度や情報発信力の差が、応募数に直結します。特に中小企業は、自社の魅力を効果的に伝えることが重要です。
情報発信のポイント:
- 具体的な仕事内容の紹介
- 社員のリアルな声の発信
- 職場の雰囲気が伝わる写真
- 成長機会のアピール
最近では求人サイトの口コミも重視されています。ネガティブな口コミがあれば、その改善に取り組むことも必要でしょう。
採用管理ツールを導入する
採用業務の効率化には、適切なツールの活用が欠かせません。特に応募者が多い場合、手作業での管理では限界があります。
ツール導入のメリット:
- 応募者情報の一元管理
- 選考状況の可視化
- 面接日程調整の自動化
- 評価データの蓄積と分析
初期費用は掛かりますが、長期的に見れば人的コストの削減につながります。ただし、ツールに依存しすぎず、あくまでも採用担当者の業務を支援するものとして活用することが重要です。
フォロー体制を充実させる
採用成功の鍵は、内定後のフォローにあります。この時期のコミュニケーション次第で、入社後の定着率が大きく変わってきます。
重要なフォロー施策:
- 定期的な状況確認
- 入社前研修の実施
- 配属先との交流機会
- 不安や疑問への丁寧な対応
特に気を付けたいのが、入社後のギャップ防止です。企業の良い面だけでなく、課題や困難な部分についても適切に情報提供することで、ミスマッチを防ぐことができます。
採用力を高める!組織で取り組むべき施策とは
採用は人事部門だけの仕事ではありません。全社を挙げて取り組むべき重要な経営課題です。ここからは、組織として実施すべき施策について紹介します。
一朝一夕には改善できない課題もありますが、今できることから着実に進めていくことが、採用力向上への近道となります。
採用担当者のスキルを向上させる
採用の成否は、採用担当者の力量に大きく左右されます。特に以下のスキルは重点的に強化する必要があります。
- 面接技術の向上
- 適切な人物評価
- 魅力的な企業説明
- 応募者とのコミュニケーション
ただし、すべてを採用担当者任せにするのは危険です。採用基準や評価方法を標準化し、担当者が変わっても一定の質を保てる仕組みづくりも重要です。
外部の専門家を活用する
すべてを自社で抱え込む必要はありません。状況に応じて、外部の専門家の力を借りることも検討しましょう。
活用できる外部リソース:
- 採用代行サービス
- 採用コンサルタント
- 人材紹介会社
- 研修専門会社
特に採用ノウハウが不足している企業は、外部の知見を活用することで、採用力を大きく向上させることができます。ただし、丸投げは禁物。自社の特徴や課題をしっかり共有し、二人三脚で進めることが成功のポイントです。
中長期の採用計画を立てる
場当たり的な採用では、良い結果は望めません。3〜5年先を見据えた計画的な採用活動が必要です。
計画に盛り込むべき要素:
- 将来の必要人員数
- 採用時期と人数配分
- 予算配分の見通し
- 人材育成計画との連動
特に重要なのが、「採用」と「育成」の連動です。入社後の育成体制を踏まえた採用計画でないと、せっかく採用しても活躍してもらえない可能性があります。現場の受入体制と連携しながら、実現可能な採用計画を立てていきましょう。
まとめ
採用難を解決する第一歩は、自社の課題を正確に把握することから始まります。採用基準や選考プロセスの見直し、企業の魅力発信強化など、できることから着手していきましょう。
また、採用市場の変化に柔軟に対応しながら、中長期的な視点で採用戦略を立てることも重要です。
すぐに結果が出る問題ではありませんが、この記事で紹介した施策を一つずつ実行に移すことで、確実に状況は良い方向に向かっていきます。
まずは自社の状況に合わせて、優先順位の高いものから取り組んでみてください。採用成功への道は、その一歩から始まるのです。
弊社公式LINEでは、定期的に経営者や採用担当 / 人事の方に向けて採用に関する有益なトピックスを紹介しておりますのでもしよろしければ、下記バナーよりぜひご登録ください。



や採用コンサル会社を選ポイント@1.5x-1.jpg)