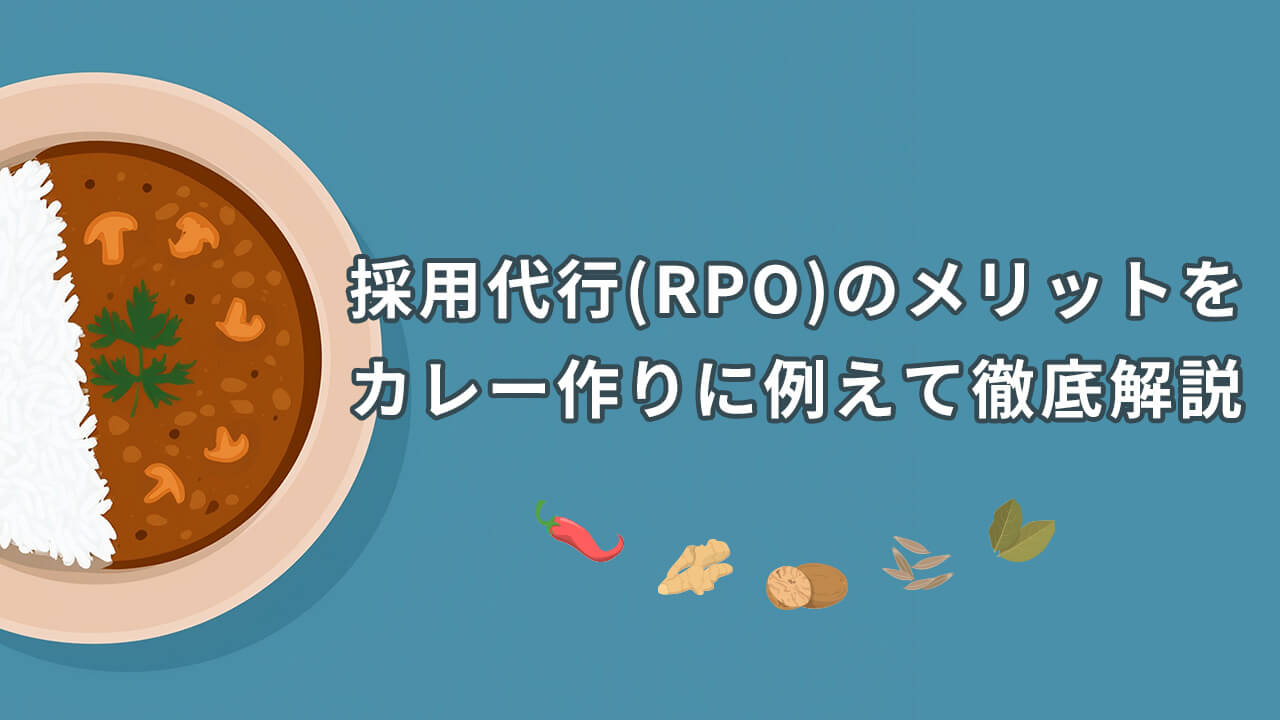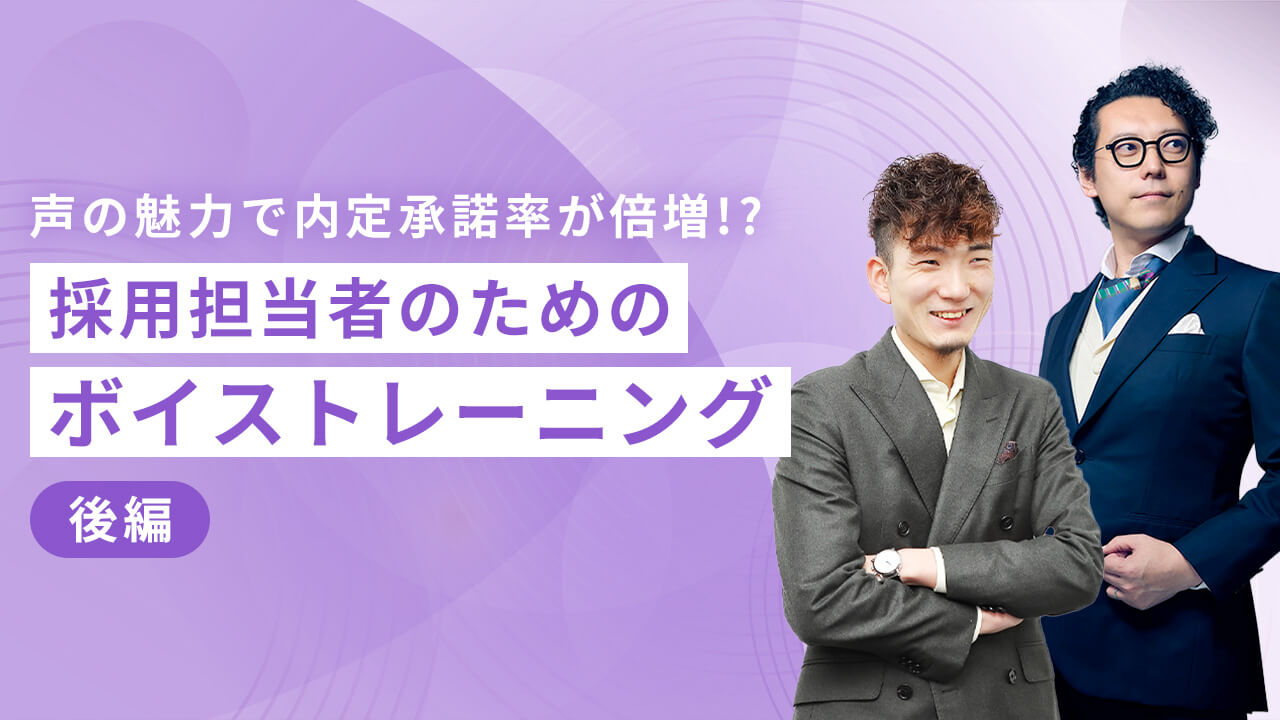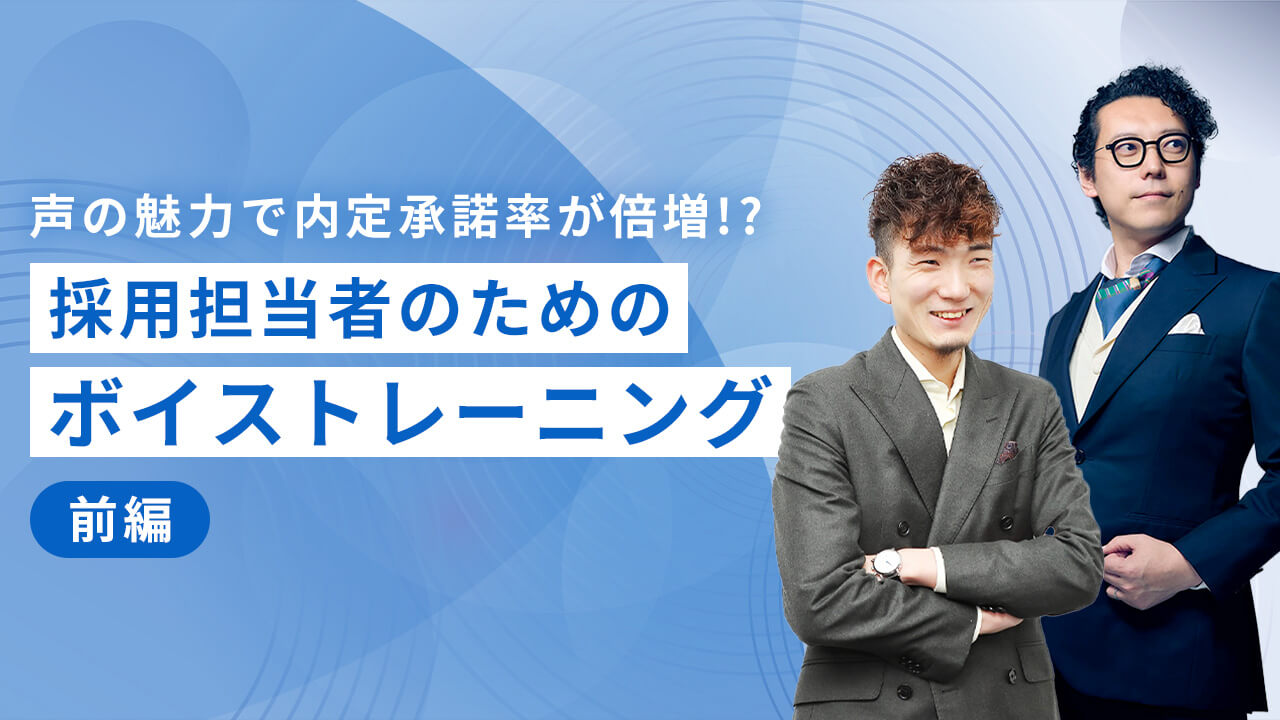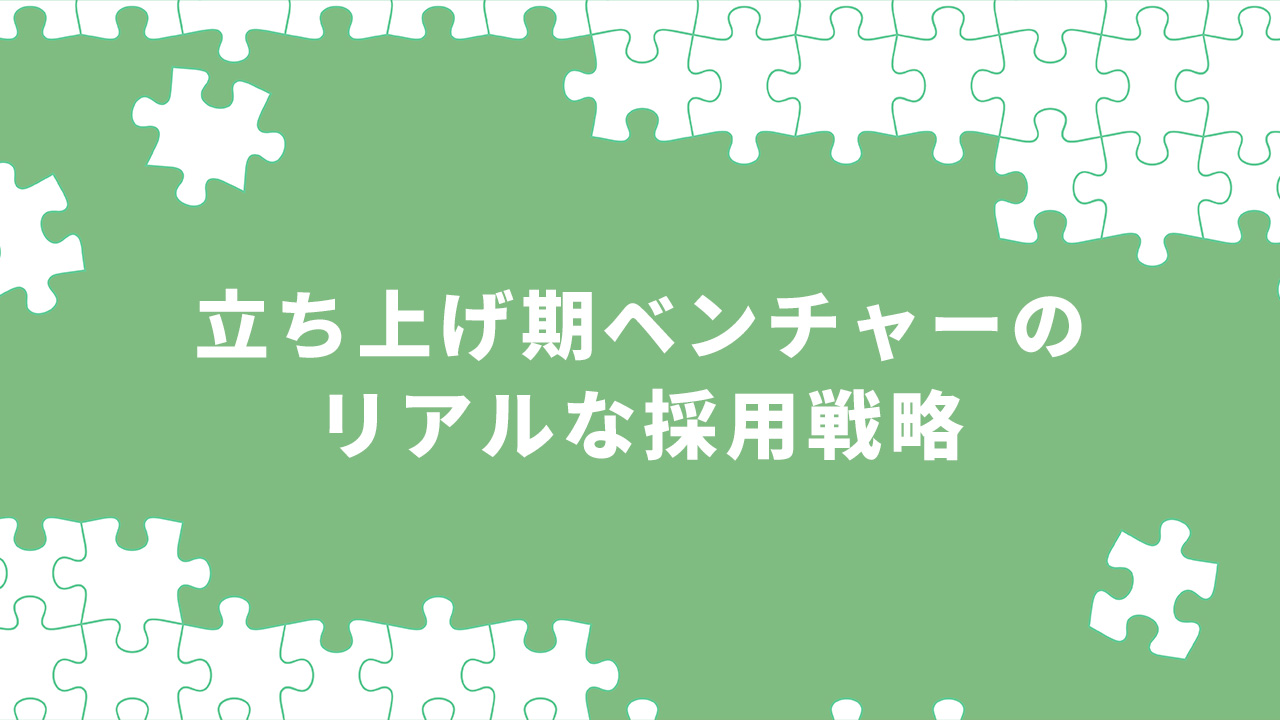
近年、立ち上げ期のスタートアップ企業やベンチャー企業が「理念採用」を掲げるケースが増えています。
「うちはまだ給料は高くないけれど、やりがいはある」「裁量は大きく、成長環境も整っている」「やったら、やった分だけインセンティブがつく」「夢を一緒に追いかけられる仲間がほしい」
──そんな言葉を掲げ、情熱ある仲間の参画を期待する企業さんも多いと思います。
しかし、こうした理念採用は、決して“想い”だけで成立するものではありません。
理念で人が動くのは、それを支えるプロダクトや実績、そして社会に与えるインパクトが明確に存在しているときです。
何もない段階で「想い」だけを売りにしても、候補者からすれば、それは単なる“都合の良い話”に過ぎません。
さらに言えば、今の求職者の多くは、まず“生活”と“キャリアの安定”を求めており、そこに乗る形で「理念」や「社会的意義」が加わるものです。
本稿では、なぜプロダクトのない段階での理念採用がうまくいかないのか、そして立ち上げ期の企業がとるべき現実的な採用戦略について整理していきます。
監修者

株式会社Revive代表
熊野拓人
法人向けにインフラ系商材の電話営業を行い、キャリア内で全国売上No.1の販売代理店において新人賞を3ヶ月で獲得。営業人材の育成、営業業務の代行を主軸に2021年株式会社Reviveを設立。2年で計100名以上の営業組織を構築し、50社以上の営業プロジェクトに携わる。後に動画やWebにおけるクリエイティブの制作から採用支援サービスを開始。現在では採用計画の立案から、一次面接の代行までを請け負う総合的な採用支援活動を行い、中小企業を中心に約50社以上を採用成功に導く。

株式会社Revive代表
熊野拓人
法人向けにインフラ系商材の電話営業を行い、キャリア内で全国売上No.1の販売代理店において新人賞を3ヶ月で獲得。営業人材の育成、営業業務の代行を主軸に2021年株式会社Reviveを設立。2年で計100名以上の営業組織を構築し、50社以上の営業プロジェクトに携わる。後に動画やWebにおけるクリエイティブの制作から採用支援サービスを開始。現在では採用計画の立案から、一次面接の代行までを請け負う総合的な採用支援活動を行い、中小企業を中心に約50社以上を採用成功に導く。
目次
はじめに:年収レイヤー別に見る、転職顕在層への有効な採用手法
まず前提として、転職活動をしている人材(いわゆる転職顕在層)に対して、どの採用手法が有効かは「年収レイヤー」によって大きく異なります。以下の図は、それを視覚的に整理したものです。
年収300万円未満〜450万円前後/ボトム層
検索型・ナビ型媒体、採用SNSが中心
このゾーンは、ボリューム層かつ、最も転職意欲が顕在化している層です。
多くの求職者が**「職種+勤務地+条件」で自ら検索し、応募する**という行動をとります。
- 検索型求人媒体(例:indeed、求人ボックス、スタンバイ)
- SEO対策と原稿の条件訴求がカギ。職種×勤務地×待遇が合えば、即応募につながります。
- SEO対策と原稿の条件訴求がカギ。職種×勤務地×待遇が合えば、即応募につながります。
- ナビ型求人媒体(例:doda、マイナビ、Type)
- エージェントとの連携やスカウト配信機能もあるため、やや高めの年収帯にも対応可能。
- エージェントとの連携やスカウト配信機能もあるため、やや高めの年収帯にも対応可能。
- 採用SNS(例:Wantedlyなど)
- 条件提示よりも「雰囲気」や「カルチャー」に共感する若手層向き。ただし応募の質はばらつきがち。
- 条件提示よりも「雰囲気」や「カルチャー」に共感する若手層向き。ただし応募の質はばらつきがち。
この層は“検索される前提”であるため、募集ポジションの明確さと原稿の打ち出し方が極めて重要です。理念よりも条件と環境訴求で勝負すべき領域です。
年収450〜650万円/ミドル層
人材紹介・スカウト媒体が強い
この層になると、「条件が合えば転職したい」という受け身だけど有望な転職顕在層が多くなります。
彼らは今の会社に不満はないが、成長意欲やキャリア形成の観点で情報を収集しているフェーズ。もしくは、何かしらの理由により転職しないといけない状況にあるが、猶予期間もあるため積極的には動いていない。という層が多く存在します。
- 人材紹介
- キャリアアドバイザーが橋渡しをしてくれるため、年収やポジションなど、ややハードルの高い求人でもアプローチ可能。
- 曖昧な求人内容では候補者に響かないため、ポジションのミッション・成長環境・チーム構成など詳細な説明が必須。
- スカウト媒体(例:ビズリーチ、ミイダス)
- 指名感を持ってアプローチできるため、転職理由が明確でない層にも響く。
- スカウト文面のパーソナライズと、企業の見せ方が勝負どころ。
このゾーンでは、やりがいや成長環境への訴求が少しずつ効果を持ち始めるため、戦略的に組み込むと良いと言えます。
年収700万円以上/トップ層
ヘッドハンティング・LinkedInなどピンポイント施策
この層は人数自体が少なく、受け身の転職顕在層はさらに希少です。
そのため、通常の求人媒体では届かず、ピンポイントでのアプローチが求められます。
- ヘッドハンティング
- 業界に強いエージェントを通じて、水面下で打診。役職や専門性が高くなるほど効果的。
- 条件・ポジションの魅力だけでなく、「なぜこの人に声をかけたのか」という文脈が重要。
- LinkedIn
- グローバル人材やIT系に特化したタレントへの直接アプローチが可能。
- 他社と差別化できる明確なビジョンや社会的意義がないと、反応率は低下する。
ここでは、「理念」や「会社の社会的意義」などがようやく意味を持つ領域です。
つまり、この年収ゾーンに達して初めて、理念採用が戦略として成立しうるということになります。
年収レイヤー毎の特徴まとめ
| レイヤー層 | 年収目安 | 転職活動の傾向 | 有効な手法 | 訴求すべきポイント |
| ボトム層 | 〜500万円 | 顕在層が多い (今すぐ転職したい) | 検索型媒体 ナビ媒体 採用SNS | 条件提示 働きやすさ 職場環境 HPがイケてるか |
| ミドル層 | 500〜700万円 | 顕在・潜在の中間層 (条件次第で動く) | 人材紹介 スカウト媒体 | 成長機会 ポジション キャリアパス |
| トップ層 | 700万円〜 | 潜在層中心 (滅多に動かない) | ヘッドハンティング | 理念 社会性 経営参加 裁量 影響力 |
第1章:理念採用が成立する前提条件
採用市場において、「理念採用」が成立するには明確な前提条件があります。
それは、“理念”という無形の価値を、候補者が「信じられるだけの裏付けがあるかどうか」です。
実際、多くのベンチャー企業が理念を語ります。「挑戦を大切にしている」「変化を楽しめる人と働きたい」「社会を良くしたい」。どれも素晴らしい言葉です。しかし、それが候補者に響くかどうかは、企業側の「語る力」ではなく、「実体」との整合性によって決まります。
ここで重要になるのが、前章で紹介した年収レイヤーの考え方です。
理念が刺さるのは、トップレイヤーから
図を見てわかる通り、「理念」や「社会的意義」に価値を感じて転職を検討するのは、年収レンジが600万円〜800万円以上のトップ層です。この層は、基本的な条件面(収入・安定性)が満たされており、次に「誰と、なぜ働くか?」という**“意味報酬”**に重きを置き始めます。
この層に響く採用手法としては、ヘッドハンティングやLinkedInのようなハイタッチセールスが有効です。いわゆる、何もないところからいきなり声をかけても、面白がってもらえる要素があれば、面白がってくれる人種です。
このレイヤー層の人々は、会社の“理念”に共感して動くというよりも、「この会社は何を成し遂げようとしていて、そこに自分がどのように貢献できるか」を自ら判断します。
収入がある程度保障されていることは前提で、そのうえでどこで働くかを重視しています。
つまり、理念採用を成立させるには、次のような裏付けが不可欠なのです。
- プロダクトが存在しているか?
- 顧客がいて、課題解決が行われているか?
- 顧客がいて、課題解決が行われているか?
- 社会に対する影響の兆しがあるか?
- 業界をどう変えようとしているか?どんな声が届いているか?
- 業界をどう変えようとしているか?どんな声が届いているか?
- 自社で働くことに、他社にはない意味があるか?
- 技術的挑戦・思想的スタンス・未来の構想など
- 技術的挑戦・思想的スタンス・未来の構想など
一方、理念採用が空振りに終わるパターン
一方で、まだプロダクトも世の中に出ていない、もしくは受託や営業代行のような代理的ビジネスを展開している状態で思想などを明確に発信していない段階で、「理念」を前面に出しても効果はほぼありません。
なぜなら、候補者がその理念を“確かめる術がない”からです。
たとえば、業務内容が他社と同じ、報酬も市場平均以下、それでいて「やりがい重視」「理念に共感できる人に来てほしい」というメッセージを出しても、応募は集まりません。
むしろ、「条件が悪いから理念を押しているだけでは?」と逆効果になることさえあります。
ここで見失ってはいけないのは、理念採用とは「企業の都合」ではなく「候補者の選択」だということ。
理念で人が動くのは、それが信じられるだけの土台があるときだけなのです。
要は、採用向けに取ってつけたような理念では人は動かず、それをサービスや行動規範としてどれだけ落とし込めているか?という点が重要という事です。
理念採用の“本質”は実行力に宿る
理念とは、経営者が語るストーリーではありません。
組織が日々の行動で体現しているものです。
候補者は理念そのものよりも、「それがどう行動に現れているか」「働く人がどういう思考で動いているか」を見ています。
つまり、理念採用とは、日々の事業活動と組織文化の中でにじみ出るものであり、後から貼り付けるものではないということです。
理念採用が成立する企業には、必ず「言葉と行動の一致」があります。逆にそこが一致していない企業は、どれだけ理念を強く打ち出しても、採用では勝てません。
採用に勝てない企業の例
① 「裁量があります!」と言いながら、すべてトップダウンな企業もしくは成果主義
表向きのメッセージ:
「一人ひとりが経営目線を持ち、自律的に動ける組織です」
実際の現場:
- 重要な意思決定はすべて経営陣かTOP成績を残したメンバーのみが行う
- メンバーは“指示待ち”が正解になっている。実行ベースの業務体系
- 新しい提案や挑戦に対して「今はそのタイミングじゃない」とブロックされる
結果:
せっかく裁量を求めて入社した優秀な人材が、数ヶ月で「話が違う」と離職。口コミにも“ギャップが大きい”と書かれ、応募数自体が落ちる。
② 「成長環境です」と言いながら、教育もフィードバックもない企業
表向きのメッセージ:
「圧倒的なスピードで成長できるベンチャーです」
実際の現場:
- OJTという名の放置
- 明確な目標も評価基準もない
- フィードバックや1on1が形骸化している、評価基準もわからない
結果:
“成長”を求める20代が疲弊し、「自己責任」の空気に違和感を抱いて早期退職。採用広報で謳っていた“成長ストーリー”が嘘に見えてしまう。
そもそも成長って何をもって成長したととらえるのかが明確になっていない。(これはお互いに)
③ 「社会にインパクトを」と言いながら、代理店ビジネスに依存している企業
表向きのメッセージ:
「社会課題に挑むプロダクトで、未来を変えていく」
実際の現場:
- 事業の大半は他社商材の販売代理・OEM受託
- 自社プロダクトは構想段階で、動いていない
- ミッション・ビジョンはあるが、社内では語られていない
結果:
求職者から「本当に社会的意義がある会社なのか?」と疑念を持たれ、理念に共感した人ほど離れていく。中長期的にブランディングが崩壊。
第2章:初期ベンチャーがやるべき「条件提示+環境訴求」の採用
では、「理念で人は動かない」フェーズにあるベンチャー企業が、採用市場で勝つにはどうすればよいのでしょうか?
結論はシンプルです。まずは候補者が転職で求める“現実的価値”に正面から向き合うこと。
理念ではなく、「条件」と「環境」で戦うことが、初期フェーズの企業にとって最も合理的で、再現性のある戦略と言えます。
理想ではなく、現実的に市場に対して自社が価値のある会社なのか?を見ていきましょう。
という事です。
条件提示:求職者が“最初に見るもの”に本気を出す
転職活動を始めたばかりの候補者が最初に確認するのは、理念でもビジョンでもなく、「条件」です。
条件で入ってきた人は、他の条件の良い会社にすぐに転職するから~という事をいう、ブランディング系の企業さんやコンサルの方もいるとは思いますが、それは入社後のオンボーディングや日々のカルチャー浸透で防ぐことが出来ます。
ボトム層からミドル層の採用において、母集団形成の点で条件面が重視されていることは事実です。
- 年収はいくらか
- 勤務地やリモート可否
- 働き方の柔軟性
- ポジションの責任範囲
- どんなスキルが身につくのか
この「条件」の精度が低い、あるいはあいまいな表現しかできていない企業は、それだけで母集団形成に失敗します。
よくあるのが「年収300〜800万円(経験・スキルによる)」という幅広すぎるレンジ。これは実質「安くてもいい人がいればラッキー」と読まれ、信頼を損ねます。
あと、シンプルに不安になります(笑)
焼肉屋さんに行くときに食べログを見たら、想定予算が2,000円~40,000円と記載があったら、おそらくその焼肉屋さんにはいかずに、他の焼肉屋さんを検討するはずです。
よっぽど魅力的な写真やブランドとしての価値があれば、お店に問い合わせの電話をするかもしれませんが、日によって変わるので何とも言えません。と言われたらよっぽどの物好き以外は予約をしないでしょう。
重要なのは、「どのような経験がある人に、どれくらいの対価を払えるか?」を明示すること。これは条件提示でありながら、企業としての“スタンス”でもあります。
いい人が居たら、それは良い条件を出すというのはわかるんですけどね(笑)
環境訴求:「働く体験価値」で選ばれるために
そして次に重要なのが、「環境訴求」です。
特に20〜30代前半の層は、「この会社でどんなふうに働けるのか?」を非常に気にします。
彼らは会社の理念そのものよりも、「その理念をどう行動で体験できるのか?」に注目しているのです。
たとえば、以下のような情報が刺さります。
- 経営陣との距離が近い。日常的に意思決定プロセスを見られる
- 年齢や社歴に関係なく意見が通るカルチャー
- 入社1年目でもプロダクト開発や営業戦略に深く関われる
- 急拡大中で役割が流動的、だからこそ成長できる
こうした“働く実感”が伝わると、候補者は「自分がそこで働くイメージ」を持てるようになります。理念がまだ育っていない企業にとって、この「共感」は最初の突破口になります。
求職者は「理想」よりも「比較」で動く
多くの企業が、「理念」や「カルチャー」によって他社と差別化しようとします。
しかし、求職者はまず、「今の職場より良い条件か」「自分に合っている環境か」で比較をします。
「ウチは挑戦できる環境です」では弱いのです。
「入社1ヶ月で提案が採用された事例」や「実際に未経験からPMになった人のキャリア」を具体的に伝えることで、初めて差別化になります。
この点で言えば、初期ベンチャーこそ、
- 社員インタビュー
- オウンドメディアでの発信
- カジュアル面談での体験共有
などの体験設計型の採用活動をもっと積極的に行うべきです。
条件×環境=信頼
結局、求職者は企業の“理念”そのものより、「この会社に入って大丈夫か」「自分が成長できるか」を見ています。
その信頼は、「わかりやすい条件」と「具体的な環境」でしか担保できません。
理念採用が成立するのは、信頼と共感がすでに獲得できている企業です。
まだそのフェーズにないなら、「まずは信頼を勝ち取る設計を、条件と環境から始める」──これが、今の市況に合った採用戦略と言えます。
第3章:マズローの欲求5段階説・7つの習慣から見た採用フェーズ
採用戦略は、単に「人を集める手段」ではありません。
それは、**候補者の心理状態=今どのフェーズにいる人に、どんな“報酬”を提示すれば動くのか?**という、心理的な要素の上に設計されるべきものです。
この構造を理解するのに最も役立つのが、心理学者マズローの欲求5段階説と、スティーブン・R・コヴィー博士の『7つの習慣』です。
マズローの欲求5段階と採用訴求の順序
マズローの理論によれば、人の欲求は次のような5段階に分かれています
- 生理的欲求(衣食住など)
- 安全欲求(雇用・健康・生活の安定)
- 所属と愛の欲求(仲間、チーム、帰属意識)
- 承認欲求(評価、ポジション、収入)
- 自己実現欲求(使命感、創造性、理念への共感)
このうち、初期ベンチャーがターゲットとする転職顕在層の多くは、まだ「2〜4」のゾーンにいます。
つまり、「生活の安定」「職場の安心感」「キャリアアップ」など、極めて現実的なニーズを満たした上で、ようやく「理念」や「社会的意義」が視野に入ってくるのです。
理念採用が成立するのは、自己実現フェーズにある“キャリア後半層”や、既にある程度満たされた人材です。
逆に、それより前のフェーズにいる人に対して理念を打ち出しても、それは“遠すぎる話”に感じられてしまうのです。
『7つの習慣』:私的成功なくして、公的成功なし
『7つの習慣』においても、成長には「私的成功 → 公的成功」という順序があると説かれています。
- 私的成功:自己責任を持ち、主体性を発揮し、目標を達成する力を身につける
- 公的成功:他者に貢献し、チームや社会に影響を与える
企業が「社会性」「意義」「ミッション」を訴求するのは、まさにこの“公的成功”に働きかける行為です。
しかし、候補者がまだ「自分のキャリア形成」「スキルアップ」「収入安定」といった“私的成功”を追っている段階であれば、共感は得られません。
特に、20代〜30代前半の若手に対して「理念共感型採用」を仕掛けても空振りする理由が、まさにここにあります。
彼らはまだ、自分の基盤をつくっている最中なのです。
フェーズに合ったメッセージを設計する
ここまでの話をまとめると、「理念訴求は早すぎると逆効果」になる構造は、こう表現できます:
- 条件提示は「生理的・安全欲求」に対応(私的成功の入口)
- 環境訴求は「所属・承認欲求」に対応(私的成功の加速)
- 理念訴求は「自己実現欲求」に対応(公的成功への橋渡し)
採用活動とは、この階段を設計するプロセスなのです。
だからこそ、初期ベンチャーが理念だけを掲げて採用に挑んでも、成果が出ないのは当然です。
まずは候補者が“何を求めているか”を正しく読み取り、そのフェーズに対応したメッセージを丁寧に設計すること。
理念は、その先にある“報酬”であり、最初に出すものではないという理解が不可欠です。
第4章:理念採用を語るなら、その土台を整えよ
ここまで見てきたように、「理念採用」は非常に魅力的な言葉である一方で、採用の初期フェーズにおいては極めてリスクが高い戦略でもあります。
理念で人が動くのは、候補者が一定のキャリアステージに到達しており、企業側にもそれを支えるだけの実績と構造がある場合に限られます。
では、自社がその段階にないとき、理念採用は全く機能しないのか?というと、そうではありません。
“理念”を表に出す前に、裏側の土台を整えることが重要なのです。
理念採用の前提条件チェックリスト
以下の問いに「はい」と答えられる数が多いほど、理念採用を打ち出す準備が整っていると言えます。
- 自社のプロダクト・サービスに独自性があり、明確な顧客価値がある
- 業界内で一定の知名度や成果があり、社会的な評価を得ている
- 組織の中で理念が共有されており、日常業務に落とし込まれている
- 採用時点で候補者に提示できる「やりがい+報酬+成長環境」がバランスよく揃っている
- 理念を体現する社員のストーリーや行動が社外にも発信されている
これらの項目が揃っていれば、理念を軸とした採用活動は大きな力を発揮します。
しかし、1つでも大きな欠落がある場合は、理念採用を前面に出すよりも、まずは「条件と環境」で信頼を獲得する方が、現実的かつ成果につながります。
理念は、語るものではなく“にじみ出る”もの
本当に理念採用が機能している企業は、そもそも「理念採用をやろう」とは言いません。
社員の行動やサービスの設計、日々の意思決定プロセスの中に自然とその理念が組み込まれており、候補者はそこから“にじみ出るもの”に惹かれて応募してきます。
だからこそ、理念採用を実現したい企業こそ、まずは
- 候補者の視点で設計された求人原稿
- 入社後のリアルを伝えるオウンドメディア
- 社員インタビューや行動指針の公開
など、理念と実態のギャップを埋める活動を積み重ねていく必要があります。
採用は、企業の“在り方”が問われる
採用とは、単なる人集めではなく、「自社は何者で、どこへ向かうのか」を社会に問う行為です。
理念採用を目指すなら、まずはその理念が社内外に信じられるだけの構造を持っているかを見つめ直しましょう。
現実を直視し、まずは条件と環境で候補者の信頼を得ること。
そのうえで、実績と文化を育てながら、自然と“共感が集まる組織”へと進化すること。
それが、理念採用の本質的なスタートラインだと、私たちは考えます。
第5章:理念採用はどう実現していくべきか?
ここまでの内容を踏まえて、「じゃあ結局どうすればいいの?」という声が聞こえてきそうです。
理念採用は確かにハードルの高い戦略ですが、決して諦めるものではありません。
むしろ、企業が中長期的に成長していく上で、いずれ不可欠となるテーマです。
ただしそれは、順序と仕組みを間違えなければ、という前提付きです。
理念採用を成立させるためには、次のような段階的なステップが必要です。
ステップ①:まずは社内に理念を“浸透”させる
理念を採用の武器にする前に、今いるメンバーがその理念を語れる状態になっているかを確認する必要があります。
そのためには、まず社内で**MVV(Mission・Vision・Value)**を整理・再確認し、それを日々の判断基準に落とし込む必要があります。
ここで重要なツールとなるのが、**クレド(行動指針)**です。
クレドは、単なるお題目ではなく、「この組織では、どう行動することが価値とされるのか?」を明文化したものです。
これがあることで、チーム内での意思決定や評価が一貫し、理念が“文化”として機能し始めます。
この段階では、外部への発信ではなく、社内メンバーに“理念が腹落ちしている状態”をつくることが最優先です。
例えば、私が過去に在籍していた営業系の企業では、月間での目標数値に対しての達成or未達で評価が完全に分かれていました。
朝定刻通りに出社をし、定時まで頑張って8時間働いたけど、その日の売上が0円の社員と、前日に深酒をして定刻から2時間遅刻して、しかも2日酔いで出社をしたけど売上をその日で50万作った社員では、売上を50万作った社員が評価されます。
少し極端な組織ですが、はっきりしていて私には居心地が良かったです。
おかげでこの組織で私は、残業というものをしたことがありません(笑)
ステップ②:プロダクトで勝負できないなら、人間関係で勝負する
理念を社内に浸透させる土台が整ったら、次に取り組むべきは**リファラル採用(社員紹介)**です。
立ち上げ期のベンチャーやプロダクトが未成熟な企業にとって、求人広告や媒体からの採用はハードルが高くなります。
そうした中で有効なのが、今いるメンバーが“この人と働きたい”と思う人材を直接口説いてくる、つまり“人間力勝負”の採用です。
このフェーズでは、SNSでの発信やカジュアル面談が効果を発揮します。
“会社の理念”ではなく、“この人が言うなら信じられる”という信頼の連鎖で、組織が少しずつ広がっていきます。
ステップ③:理念がにじみ出るチームになったら、外部発信の準備が整う
リファラルで集まった仲間とともに、MVVやクレドを共有し、日常の業務に落とし込んでいくことで、組織には“にじみ出る理念”が形成されていきます。
この段階ではじめて、広告戦略や採用広報が意味を持ち始めます。
理念やカルチャーを外部に発信しても、それが実際の組織の行動と一致していれば、候補者から見ても“嘘がない”と感じられ、共感や応募につながるようになります。
逆に言えば、この段階を踏まないまま理念採用を打ち出すと、ギャップが炎上の火種になりかねません。
これが、昨今よく聞く早期離職の現状です。
実態よりも良い情報や、理想を書くから乖離が生まれるのです。
まとめ:理念採用は“語るもの”ではなく“伝わるもの”
理念採用は、企業の本質に迫るテーマです。
しかしそれは、いきなり掲げるものではありません。
まずは信頼を獲得し、実績を積み、文化を育ててから、自然と伝わる仕組みを構築していく
──それこそが、理念採用を成立させる唯一の道です。
まず自社の足元を整え、内側から文化を醸成していくべきです。
- MVVの再確認
- クレドの構築
- リファラルでの信頼採用
- SNSでの等身大発信
- 組織全体での理念体現
こうしたステップを経てはじめて、理念採用は「共感が自然に集まる仕組み」として機能するようになります。
理念採用は、“語るもの”ではなく、“伝わっていくもの”。
そのプロセスを丁寧に設計し、時間をかけて育てていくことこそが、これからの採用戦略の中核になると、私たちは考えます。
採用とは、会社の在り方そのもの。
一時のキャッチコピーではなく、長期的に“共感が集まる組織”を目指していきましょう。